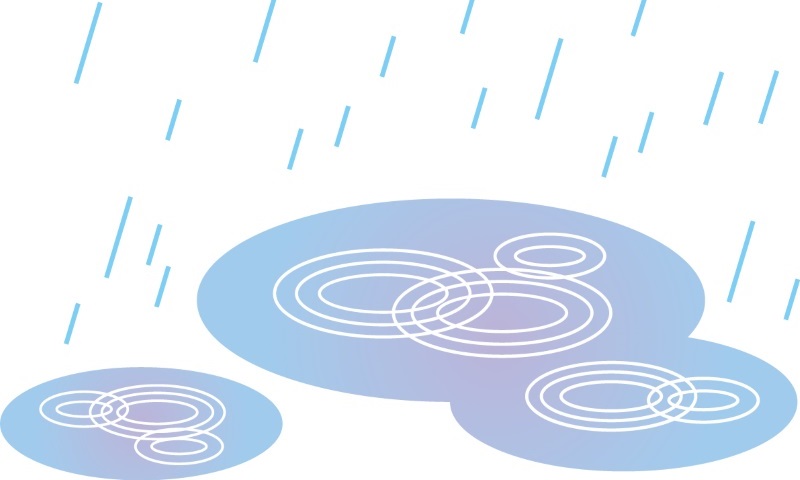もし、今、新しい仕事を求めて「職探し」をしていたとしたら、新聞販売店で働くことを視野に入れている人もいることでしょう。
勤務する場所は?給与は?待遇面は?…、自分の働くスタイルと照合をかけていくと気になる点も出てきます。
「新聞販売店って勤務が過酷じゃない?」
「休みって、ちゃんと取れるの?」
「もし、急用で休みたい時はどうするの?」
こんなことで、新聞配達という仕事に興味はあるけれど、実際のところが良くわからなくて二の足を踏んでいる…という人は気になりますよね。
そこで今回は、新聞販売店の「休日」や「有給休暇」について取り上げて見ましょう。
新聞販売店の「休日」の仕組み
まずは一般的な「休日の定義」を押さえておきましょう。
国が示す休日(労基法35条)とは、「労働契約において労働義務がないとされている日」であり、「原則として暦日、すなわち午前0時から午後12時までの連続24時間」と言っています。
また、同法では「使用者は、労働者に対して、少なくとも毎週一回の休日を与えなければならない」と定めています。
つまりは、「日を股がない1日24時間を少なくとも週1回は休日として設けなさいね、働かせちゃダメですよ!」と言っているわけです。
では、新聞販売店ではこの「休日」をどのように設けているか見てみましょう。
新聞販売店のコア(核)業務は、新聞配達です。
新聞配達(朝刊)は、おおむね月1回ある休刊日を除き、毎日各家庭に配られます。
その配達員は、原則、各配達エリアを一人で任されます。
そう考えると、「配達員だと休刊日以外は休めない?」と言うことになります。
しかし実際のところ、雇用形態に関係なく、ほとんどの新聞販売店では配達員に最低でも週に1回~の休みを設けています。
そうなると、担当するエリアの配達員が休んでいる日の配達は誰が行うのでしょうか?
これには、「代配」や「臨配」という仕組みでカバーしています。
「代配」とは、配達エリア担当者が休みの時に、他のスタッフが変わりに配達することを言います。
各販売店にもよりますが、店長などの責任者が受け持つことが多いようです。
もう一つの「臨配」も代配と似たような仕組みですが、この場合、代配専門に人材を派遣している外部の会社に依頼して穴埋めを行うと言うものです。
これら「代配」や「臨配」を組み合わせたシフトによって、各販売店は配達員に対して週に一度以上の休みを安定して設ける仕組みを作り上げているわけです。
この仕組みは、通常の休日だけでなく、配達員が病気や体調不良により急な休みにも発動されます。
新聞販売店の「有給休暇」の仕組み
ここもまず、「有給休暇の定義」から押さえておきましょう。
国が示す有給休暇(労基法39条)とは、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えられなければならない。」と言っています。
何やら難しい表現ですが、つまり「雇った日から6ヶ月間ずっと在籍して、休日を除いた8割以上の日をちゃんと働いたすべての従業員に、年10日以上の有給休暇をあげなきゃダメですよ!」と言っているわけです。
ここでのポイントは、「すべての従業員(労働者)」と言う点です。
法律では、正社員はもちろん、アルバイトでもパートでも基準を満たせば有給休暇が適用されるということです。
有給休暇の日数が年10日以上となっていますが、これは実際の勤続年数や労働日数、所定労働時間などによって段階的に年間最大20日まで取れるように規定されています。
この有給休暇制度は、もちろん新聞販売店で働くすべての方にも同じように適用されます。
入社後、自分が有給休暇を取れる要件を満たしていれば、原則、自由に行使できるわけです。
ただし、「自由」と言っても、いきなり上司に「明日、有給休暇をいただきますね」と言って、休まれてしまうと業務に支障をきたしてしまうことも考えられます。
また使用者にも、その日に休まれては正常な業務の妨げられる場合には、変更してもらう権利(=時季変更権)が与えられています。
やはり、新聞販売店側も代配の手配などが必要ですので、緊急性がない場合は、十分前もって希望日を出ししておくことがマナーとも言えます。
やはり、互いがスッキリした気持ちで休む、休んでもらうことが理想的な形と言えるでしょう。
国が定める有給休暇の詳しい内容については、厚労省発行のハンドブックを参考までにあげておきます。
まとめ
このように休日や有休休暇については、国が定めた法律によって労働者の権利がしっかり定められていますし、事業者側も「忙しいから」という理由で従業員に休暇を取らせないと、それは違法になります。
よく、「日本人は休み下手」と言われたりしますが、ワークライフバランスの考え方によって、「上手に休み、しっかり仕事をする」というメリハリある働き方ができる、そして、それらを提供していく職場づくりが今後一層支持されていくことでしょう。